6歳児の視力発達は、子供の健康と成長にとって非常に重要な課題です。
どの家庭にも、タブレットやスマホ、携帯ゲーム機が当たり前のようにある環境。
幼児期から視力低下することが、珍しいことではありません。
また、小学校の授業でもタブレット化が進むことで、さらに視力を低下させることも考えられます。
現在の子供は、昔と比べると視力発達に悪影響を及ぼす可能性の高い環境なのです。
だからこそ、わたしたち親は子供の視力発達について、考えなくてはいけません。
6歳児のこの時期は視覚機能が成熟し、その後の学習能力や生活の質に大きな影響を与えます。
今回、6歳児の視力発達について、発達の過程、適切なケア、早期発見と治療の重要性などを紹介。
さまざまな側面から詳しく解説していきます。
視力発達の過程
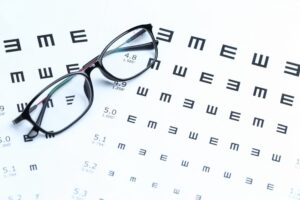
子供の視力は、生まれたばかりの頃は未発達ですが、年齢とともに徐々に発達していきます。
この発達過程を理解することが、適切なケアにつながります。
そしてわたしたち親は、子供の年齢によって子供に良い影響を与える接し方をすることが大切になるのです。
子供の視力発達を促進する遊びをすることが重要になります。
それでは、子供の視力発達について年齢別に解説していきます。
生後から1歳まで
赤ちゃんは生まれたときの視力は0.02程度で、ぼんやりとした明るさしか感じられません。
しかし、生後6か月ごろから周囲のものが見えるようになり、動くものを追うこともできるようになります。
1歳ごろには視力が0.2~0.3程度に達します。
この時期は視覚発達の基礎が培われる大切な時期です。
赤ちゃんは目の前にあるおもちゃなどを見ることで、視覚刺激を受けながら視力が発達していきます。
親が赤ちゃんと一緒におもちゃで遊んだり、絵本を見せたりすることが、視力発達を促進するのに役立ちます。
2歳から3歳
2歳ごろになると視力は0.5前後まで発達し、3歳で0.8程度に達します。
この頃になると、はっきりとしたものが見えるようになり、遠くのものも認識できるようになります。
この時期は、視覚的な経験を積むことが大切です。
外遊びをたくさんさせて、遠くの風景を見る機会を作ることで、視力の発達を促すことができます。
また、絵本やおもちゃで視覚刺激を与えることも効果的です。
4歳から6歳
4歳を過ぎると、視力は1.0に向けて着実に発達していきます。
6歳ごろには大人と同程度の視力になります。
この時期は、立体視や距離感覚、色覚など、視覚機能がほぼ完成する重要な時期です。
しかし近年、デジタル機器の普及により、この時期の子供たちが近視になるリスクが高まっています。
長時間のスマホやタブレットの使用は、目に負担がかかり視力低下の原因になるため、使用時間を制限することが重要。
また、外遊びなどで遠くを見る機会を作ることで、視力の発達を促せます。
視力の問題と対策
子供の視力発達には、様々な問題が潜んでいます。
また、その視力問題のほとんどは、日常の生活習慣が原因になることが多いです。
主な視力の問題点
- 弱視
- 近視
- 乱視・遠視
主な視力問題の原因
- パソコン・スマホなど、近い距離を長時間見続けることで毛様体筋が凝り固まる
- 眼精疲労やドライアイを引き起こす
- 度数が合っていない眼鏡やコンタクトレンズの使用
ここで、視力の問題について、具体的に説明いたします。
弱視
弱視とは、両眼の視力に大きな差があったり、片眼の視力が極端に低下している状態を指します。
原因としては、斜視や遠視、乱視などの屈折異常です。
弱視は3歳までに発見し、治療を開始することが重要。
弱視の治療法としては、視力の低い方の目に patching(目隠し)をして、良い方の目を使わせることで視力の発達を促します。
また、屈折異常がある場合は眼鏡や コンタクトレンズでの矯正が必要です。
弱視は早期発見と適切な治療により、小学校入学時までに視力の回復が期待。
治療開始が低年齢ほど効果が大きく、4歳までに治療を開始すれば95%、7歳までで75%以上が治ると言われています。
近視
近年、子供の近視化が深刻な問題となっています。
小学生の約40%が近視であり、その割合は年々増加しているといわれているのです。
原因としては、デジタル機器の長時間使用や運動不足、部屋の照明環境などが考えられます。
近視の進行を遅らせるためには、屋外活動を増やしたり、目と画面の距離を30cm以上離すなどの対策が効果的です。
また、徐々に進行する近視の場合は、定期的な眼科検査と適切な処方眼鏡の使用が重要になります。
乱視・遠視
乱視は物が歪んで見えたり、かすんで見える状態を指します。
遠視は近くが見えにくい状態です。
これらの屈折異常は、視力の発達を阻害する可能性があるため、早期発見と適切な処置が必要不可欠になります。
乱視や遠視がある場合は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正します。
子供用のフレームを選び、かけ心地が良く似合うものを選ぶことが大切です。
定期的に眼科を受診し、視力の変化に合わせて処方を見直すことで、視力の発達を促進できます。
どのような視力の問題にしても、早期発見と適切な対策が不可欠となります。
定期的に眼科を受診したりすることが重要なのです。
健診と早期発見の重要性
視力の問題は、早期に発見し、適切な治療を行うことが大切です。
そのために、定期的な健診の受診が推奨されています。
主な健診については、以下を参考にして下さい。
3歳児健診
3歳児健診は、視力発達の確認と弱視などの早期発見を目的としています。
この時期までに視力が十分に発達していない場合は、その後の視力発達に影響を及ぼす可能性があるためです。
健診では簡易的な視力検査が行われますが、もし異常が見つかった場合は、専門の眼科を受診することが推奨されます。
3歳までに適切な治療を開始することで、小学校入学時までに視力の回復が期待できます。
就学時健診
就学時健診では、小学校入学前の視力検査が行われます。
この時期は視覚機能がほぼ完成する重要な時期であり、近視や乱視、遠視などの問題が見つかることもあります。
健診で視力に問題があると指摘された場合は、必ず専門の眼科を受診することが大切です。
早期発見と治療により、学習能力の低下を防ぐことができます。
家庭でのチェック
健診以外にも、家庭でも簡単に子供の視力をチェックすることができます。
お気に入りのおもちゃや絵本を使って、物を見る様子を観察したり、ボール遊びをして手と目の協調性を確認するなど、視力の変化に気を配ることが大切です。
もし何か異常が見られた場合は、早めに眼科を受診することをおすすめします。
子供自身は見えにくさを自覚していないことが多いため、親が気づくことが重要なのです。
視力を守るためのケア

適切なケアを心がけることで、子供の視力の発達を促進し、問題の発生や進行を抑えることができます。
幼児期からスマホやタブレットなどのデジタル機器に触れることが多い場合は、親が子供のケアをすることが大切です。
子供の視力を守る為に、どのような事をすれば良いのでしょうか。
デジタル機器の適正使用
スマホやタブレット端末、テレビなどのデジタル機器は、目に大きな負担をかけます。
blue lightの影響や、近くを見る姿勢が原因で、近視などの視力低下を引き起こす可能性があるのです。
そのため、デジタル機器の使用時間を制限し、長時間の使用は避けることが重要です。
30分に1回程度は休憩を取り、その際には遠くを見るようにしましょう。
また、部屋の照明を適切に調整し、目に優しい環境を作ることも大切です。
屋外活動の促進
外遊びなどの屋外活動は、視力の発達を促進する効果があります。
遠くのものを見る機会が増えるだけでなく、自然光に当たることで目の疲労を和らげることができるのです。
その為には、子供に外で遊ばせる機会を作ることが重要です。
近所を散歩したり、公園で遊んだりするのが効果的でしょう。
また、習い事や部活動を通じて、外で活動する時間を確保するのも一案です。
姿勢への配慮
近くを見る際の姿勢が悪いと、目に大きな負担がかかります。
本を読んだり、デジタル機器を使用する際は、正しい姿勢を心がけましょう。
本やタブレットは30cm以上離し、背すれから20~30度の角度で見るようにします。
また、適度な明るさを保ち、まぶしすぎないよう気をつけることも大切です。
正しい姿勢と環境を整えることで、目の負担を軽減できます。
まとめ
6歳児の視力発達は、その後の生活の質に大きく影響します。
生後から6歳頃までの時期は、視覚機能が発達する重要な時期です。
子供の視力発達を促進するためには、定期的な健診を受けて早期発見・治療に努めること、適切なケアを心がけること、そして環境への配慮が不可欠です。
親がその大切さを理解し、子供の視力に関心を持ち続けることが何より重要なのです。
子供一人ひとりの健やかな成長と、豊かな視覚体験を実現するため、私たち大人ができる最大のサポートをしていきましょう。

よくある質問
6歳児の視力発達の重要性は何ですか?
この時期の視覚機能の発達は、その後の子供の学習能力や生活の質に大きな影響を与えます。視力が適切に発達しないと、様々な問題が生じる可能性があるため、早期発見と適切なケアが重要となります。
子供の視力発達にはどのような問題があるのですか?
代表的な問題として弱視、近視、乱視、遠視などの屈折異常が挙げられます。これらは視力の発達を阻害する可能性があるため、早期発見と適切な治療が必要不可欠です。
子供の視力を守るためのケア方法はどのようなものがありますか?
デジタル機器の適正使用、屋外活動の促進、正しい姿勢の確保などが効果的です。長時間の機器使用は目への負担が大きいため制限し、遠くを見る機会を設けることで視力の発達を促進できます。
視力発達のチェックはどのように行えばよいですか?
定期的な健診の受診に加え、家庭でも簡単にチェックできます。お気に入りのおもちゃや絵本を使って子供の視る様子を観察したり、ボール遊びをして手と目の協調性を確認するなどが効果的です。



